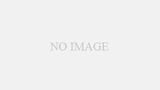定款を作成する場合、「〇〇できる」という文言を「〇〇する」と誤解される方が非常に多いです。
定款によく慣れた方と、文言をあまり気にせず、とりあえず公証人に認証してもらえる定款を作成すれば良いと考えている方は別ですが、真面目で初めて定款を目にされるような方は、大体これを誤解されています。
平成の会社法への移行等で、定款の自由度はそれまでと比べて非常に高くなりました。
そうすると、絶対に決めなければならない「絶対的記載事項」だけでなく、定款に記載すれば効力を生じる「相対的記載事項」や任意で記載できる「任意的記載事項」が多く記載されるようになります。
例えば、株式会社における役員についての事項は絶対に記載しなければいけません。
しかし、一般社団法人等における「副理事長〇名を置くことができる」などという条文も記載することができます。
この副理事長などは、「できる」なので、置かなくても良いです。
いずれ組織が大きくなった時を想定して(そうなるように願いを込めて)、置くことができるようにすることが多いです。
ちょうど、中学生の学生服を大きめに作るような感じです。
ところが真面目な方は、今はないから不要です、と言われることが多いです。
もし必要になった場合、定款を変更する際に、細部まで検討しなおしになるので結構手間になるはずです。
ですから、ちょっと大き目な組織になることを目指して、このような「〇〇できる」を入れておいてほしいものです。